

�@
�������WindowsME�B�t���[����́BDEMO�ł́A�g����͈͂Ȃ�OK�ł����A�����̂�����̂����グ�܂���B
�V���Z�́A�g����̌��ɂ��A���̏o���i�ݒ�j���ς���Ă��܂��B�R�����g�́A��҂ɂ��y�ȂƂ̌��ˍ�����
�A�h���������Ȃ�������A����ȃV���Z���D�ށh�A�Ƃ������x�Ō��Ă��������B�g������ŁA�܂���������z������A���̓s�x���������܂��B�����X���A�s����Ȃ��͍̂폜���Ă����܂��B
���͕]���ł͂Ȃ��A�`�F�b�N�}�[�N�BSynthEdit�ASynthMaker�͐V�K�Ɍ���g�b�v�ŕ\����A���n�ł܂Ƃ߂܂��B
�ꕔOS�ɂ��N���s�̖�� ��Helix ��Oatmeal �@
�@
�@
�@
Clavdium �^ Fuzziest Organ Evar �^ Sandra
�@
�@
�@
�@
�@
xhip��
�@
�@
�@
Square I ��
�@
�@
�@
 |
Computer
Music�Ƃ����C�O�̎G���t�^��3�N�قǑO�ɏo�Ă������́B
|
�@
�@
|
���̗ǂ��A�i���O�V���Z������Ă���TAL�ł����A����́A�����̕����L�����悤�ŁA�v���Z�b�g�ɂ͌��ʉ��I�Ȃ��̂���������܂��B���������A�V���Z�{���̉�����ׂĂق����Ƃ���B |
�@
�@
�@
 |
���ɉ̂��V���Z�̃t���[�ł��o�ꂵ�܂����B�ꉹ�V���Z���Ⴀ��܂���A��������̂ŁA�ꉹ�{�q���̉��������Ƃ������Ƃɂ��Ȃ�܂��B
|
�@
�@
�@
�@

(SynthEdit�^C++) |
���ƂȂ��p�X���悤���Ɩ��f���Ă��܂���GUI�ł����A�Ǝ��̌����������V���Z�ł����B
|
�@
�@
�@
Grymmjack Oatmeal skins / Oatmeal��
�@
�@
 |
�T���v���[��Shortcircuit(EUR/$135)���A�Ȃ�ƃt���[�ɂȂ�܂����B�ڍׂ�KVR�t�H�[�����B�T�C�g�E����Shortcircuit
1 (v1.1.2)�A�����ł͂��Q�͓����܂���ł����B
|

�@ �@ |
���ŋ��̃t���[�V���Z�Ƃ��ďЉ�Ă���Helix�ł����A�L���ł��o��Ɠ����Ƀt���[�ł͖����Ȃ��Ă��܂��܂����B
�i�ȉ��A2007�N����̋L���j ����̔g�`�ʼn��F���K�����ƕς����̂ł́A����܂��A�Ǝ��̉��ɂȂ�̂͊m���B Audjoo Helix : Afterwards ��2007-11-05
�A�A�b�v�f�[�g����܂����B�ׂ��ȏC���ƃo�O�t�B�b�N�X�ŁA�������̂��̂��ς����̂ł͂Ȃ����A�f�U�C�����ω��Ȃ��B�����N���b�N���Ȃ��Əo�Ȃ������\�����f�t�H���g�ŏo��悤�ɂ͂Ȃ�܂����B�E���ɂ�LIM�ilimiter�j���lj��B
��2007-12-07�A12-09�A�L�[�^�b�`�̒x��͂��̂܂܁B�v���O�����T�C�Y�̑傫���ƁACPU�����\�͂���Ⴕ�Ă�̂ł��傤�˂��B����A�T���v����24bit�ɑΉ������悤�ł��B ��2007-12-10�A�����ŁA12-09�ł��̓L�[�^�b�`����A�}�V�ɁB�o�O�t�B�b�N�X�ŏ����͕ω������̂��B ��2007-12-15�A�A�����ďC������Ă��܂��B���F�Ő����𑝂��Ă��܂����AFilter���������u�c���Ƃ��날��B�܂��܂��A�o�O�C���͂��肻���Ȋ����B
��2007-12-19�AFixed a performance bug with the
GUI.
��2008-1-13�A���낢��ׂ��ȏC�������ꂽ�悤�ł��BGUI�̕\���������ς�A�ǂ����ȁA�Ǝv�����̂ł����A�Ȃ�ƁAGUI�����ƃt���[�Y���Ă��܂��܂����B
��2008-1-13b�A�i2008-1-14�jGUI�����ƃt���[�Y���錻�ۂ͏C������܂����B�����B�������A�ŏ���GUI��\���������ɉ�����������̂́A���ς�炸�B����͍ēxGUI��\���������Ɛ���ɂȂ�̂ł����B
��2008-1-20�A�i2008-1-21�jGUI�����������\�������悤�ɂȂ�܂����B�v���Z�b�g��Helix�̓����𑨂����[���������̂ɂȂ��Ă��܂��B�t���[�V���Z�̃x�X�g�ƌ�����Helix�ł����A����1-20�łŁA�فU�����ɒB�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���߂č�҂̕��Ɋ��ӂł��B
��2008-01-22�A�i2008-01-22�j�A�o�O�C����ACID
users �ւ̏C�����B
��2008-02-06�A�i2008-02-06�j�A�}�b�N�ł����J����AGUI�R�[�h�ł̋��ʓ_�Ƃ��Č�������A�T�C�Y���k������܂����BFilter���u�c�ꂪ��������܂����B����͊������ł��B���̑��ALFO�̃o�O�C�����B
��2008-03-02�A�i2008-03-03�j�A�摜������ƕ�����ʂ�A�F��������Ă��܂����A�P�Ȃ�F�����ł͂Ȃ��A�@�\�I�Ƀf�U�C������Ă��āA����I�ɂ��V�����Ȃ��Ă��܂��B
�@ ��2008-04-13�A�i2008-04-14�j�A����̍ő�̓����̓A���y�W�G�[�^�[�ł����A���̑���̈Ⴂ������悤�ł��B�Ȃ��������ǂ��Ȃ����悤�ȋC������̂͋C�̂����H �@
|
�@
NuBiLE��
 |
�I���K���ł��Beffect�́iEmptySquareSpinner
LE�j�ƈꏏ�iZIP�j�ɂȂ��Ă���̂ŁA�ǂ��炩�𗎂Ƃ��Η�����ɓ���܂��B
|
�@
�@
�@
�@
�@
adxhip��
�@
�@
Acquit Music Greyhound
 |
�I���K���n�ł����A���낢����H���ł��A���I�ɂ����݊�������܂��B����́A�Ƃ���
���ɂ������̂œ�ꂪ�K�v�B
|
�@
 |
FreeAlpha���V�����Ȃ�܂����B���͑@�ׂō��̂�����́B���批�̗����オ
�肪�s���A�A�^�b�N�I�ɗǍD�A���搬���͓��ɗǂ��A�S�̂̎������x�z���Ă���悤�ȁB
|
�@
�@
|
�@
�@ |
|
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
Voyager��
�@
�@
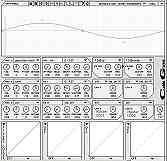 |
Wavetable synthesizer
�ł����A�A�i���O�I�B�v���Z�b�g���x�[�X�n�������ATB-303�I�Ȏw����������悤�ł��B�s�b�`�̃Y���͂Ȃ��B
|
�@
Rock��
�@
sfz��

|
Sound
Blaster�i�ȉ�SB�j�������́A�ꕔ�@��������āASF��SB�����Ńn�[�h��������邽��CPU�̕��S�ɂ͂Ȃ炸�A���C�e���V�[�̖����N��Ȃ��B �܂��Asfz�́A�g���qsfz�t�@�C����ǂݍ��ނ��ƂŁAwav�t�@�C���̃T���v���[�Ƃ��Ă��@�\���܂��B |
�@
 |
�I���K���ł��B�̂̃I���K���́A�V���Z�̂悤�ȉ��͏o���Ȃ������Ƃ������A�ǂ��A��
�����H���Ă��I���K���L�����甲���o�����͂ł��܂���ł����B
|
�@
�@
Oatmeal��

�@ �@ |
����̃W�������Ɍ��炸�A�S�Ă̖ʂɂ����āA�����x�̍����V���Z�ƌ����܂��B SKINS: PRESETS:
|
�@
�@
�@
 |
FM and AM modulation
matrix�AYAMAHA��FM�V���Z�Ƃ��Ⴄ����ŁA���F���͓�����ł��B
|
�@
Orca��
 |
�A�i���O�I��(new technology
)�Ƃ������ł����A�����łȂ���Ƃ��������B
|
�@
 |
�V���Z�E�X�g�����O�X�B |
�@
 |
�v���Z�b�g�͕ʃt�@�C���œ��E�B�ӊO�ƐF�X�ȉ����o��̂�����܂��B |
�@
 |
�N���r�l�b�g�ł��BSoundFont�ł��A�悭����܂����A��͂艹�F���삪�ł�
��Ƃ����̂��~�\�B |
�@
Crystal��
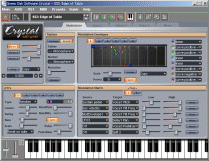 |
Crystal is a semi-modular software
synthesizer(VST Free) ����͂Ƃ��Ẵm�[�}���ȉ��F���ǂ��̂ŁA���F�f�[�^�iPatch�j���W�߂����Ƃ�
��B �����́A���[���o�^���ă��O�C������A�_�E�����[�h�ł��܂��B |
�@
 |
�V���Z�̊�{�`�Ԃł���I�V���[�^�[�A�t�B���^�[�AADSR���A���o�I�ɂ��e�Ղɂ�
���߂܂����A���F���ǍD�B |
�@
 |
�p�[�J�b�V�����n�V���Z�B�}�����o�Ƃ��́B�܂��A�P���Ȃ���ł��B |
�@
�@
�@
�@
�@